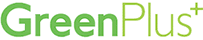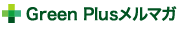今月26日、地球温暖化対策について話し合う国連気候変動枠組み条約第18回締約国会議(COP18)が、カタール・ドーハで開幕しました。日本は温室効果ガス削減の国際公約「2020年に90年比25%削減」について撤回しない方針を固めました。27日の関係閣僚委員会で決定します。COP18では、京都議定書に代わる新たな枠組み作りに向けた本格的な議論が始まりますが、達成不可能になった目標を掲げたまま交渉に臨む日本の発言力が低下する恐れもあります。【写真:カタール・ドーハで開幕したCOP18 MSN産経ニュース】
今月26日、地球温暖化対策について話し合う国連気候変動枠組み条約第18回締約国会議(COP18)が、カタール・ドーハで開幕しました。日本は温室効果ガス削減の国際公約「2020年に90年比25%削減」について撤回しない方針を固めました。27日の関係閣僚委員会で決定します。COP18では、京都議定書に代わる新たな枠組み作りに向けた本格的な議論が始まりますが、達成不可能になった目標を掲げたまま交渉に臨む日本の発言力が低下する恐れもあります。【写真:カタール・ドーハで開幕したCOP18 MSN産経ニュース】COP18では、年内に京都議定書の削減期間(第1約束期間)が終了するのを受け、その後の温暖化対策についての議論が大詰めを迎えます。事前の交渉では不公平な枠組みを早く終え、新たな枠組みの議論を進めたい日本などの先進国側と、自分たちが削減義務を負いかねない新たな議論の開始を先送りしたい途上国側で意見の隔たりが大きいままとなっています。
日本の国際公約は原発の増設を前提とし、09年に鳩山由紀夫首相(当時)が掲げましたが、、昨年の東京電力福島第1原発事故の影響で、原発頼みだった目標は行き詰まりました。
政府は9月に「30年代に原発ゼロ」を目指す革新的エネルギー・環境戦略を策定しましたが、20年の原発依存率の決定を先送りしました。環境省は年内に新たな削減目標を決定する予定でしたが、衆議院解散でさらに不透明になりました。
ところが、政府は「国際交渉に与える影響にも留意しつつ慎重に検討する」として国際公約について、撤回しない方針です。政府関係者は「今、目標の引き下げを表明したら大バッシングに遭うだけで、何もメリットがない」と話しています。一方で、達成の具体策は示されないままです。
政府は省エネや再生可能エネルギーの推進をアピールして新しい枠組みに向けた議論をリードしたいとしていますが、交渉の中でどのような役割を果たしていくのか注目されます。
(毎日新聞) (NHK NEWSWEB)