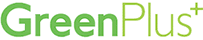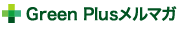この日開かれた中央環境審議会で、8月に示した3原案のうち有力案を明らかにしました。同案によると、CO2排出量が一定規模以上の企業を対象に政府が排出量の上限値を設定し、上限値からの過不足分を企業同士が売買することで、全体の削減を図ります。
上限値は、既存の省エネ技術を導入すれば達成できる水準にします。例えば鉄鋼業では先端技術で鉄1トンをつくった場合の排出量を調査。この数値に生産量なども考慮し、各社の上限値を決める想定です。
電力会社は需要に応じた電力の供給義務を負うため、総排出量では規制しません。発電量当たりの排出量を規制することで、火力発電の占める割合を減らします。発電に伴う排出量は、企業や家庭など利用者側の排出量として計算するとのこと。
ただ、先行する欧州連合(EU)をはじめ海外の制度では、電力会社にも総排出量で上限値を設定するのが主流です。将来、排出枠を国際的に流通させる場合に、整合性を問われる可能性があります。
また、既存の技術で達成可能な水準で企業の削減義務を決めるため、20年に温室効果ガスを90年比25%削減するという政府目標の達成につながるかどうかは不透明です。産業界の受け入れやすさを狙っていますが、環境NGOは不十分だと強く批判。環境省幹部は「企業に無理なことをやらせても仕方がない。省エネ対策が遅れている企業が追いつくまでの緩和措置だ」と説明しています。
経産省も制度の検討を進めてきましたが「企業の負担が増え、国際競争力が低下する」など産業界の反発が強く、まだ案をまとめていません。(asahi.com)
環境ブログランキングに参加しています。よろしければクリックご協力お願いします。