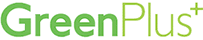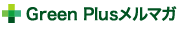県警によると、木製標識柱は、徳島市の新町川沿いや鳴門市のドイツ館周辺、神山町、板野町など4市町の6地区に設置。今年1月から作業を始め、今月22日で80本すべての取り付けを終えたとのこと。
県産材を有効活用する狙いから、県が行動計画で2010年度末までに県内で木製ガードレールを5キロ整備することを目標に掲げており、木製標識柱もそれに倣ったといいます。
メリットは、製作費が鉄製の半分で済むほか、自然景観との調和が図れる・車が衝突しても、被害が少ない・柱の復旧コストが低くすむ、などがあります。
ただ、木製のため、腐食や強度不足の心配がありますが、1998年にカラマツでできた木製標識柱を導入した北海道警では、10年以上たった現在も問題なく使用中。スギの間伐材を使っている千葉県警や愛媛県警も支障は起きていないといいます。
今回の整備で、腐食や強度などを継続的に検証し、今後、木製標識柱の設置か所を増やしていくといい、県警交通規制課は「木製標識柱を使うことで間伐材が市場に出回るようになる。間伐材の有効活用にもつながるはず」としています。(読売新聞)
木製のガードレールの安全性を心配していましたが、車が衝突した際に被害が少ないなどの利点もあり、コストや間伐材使用による資源の有効活用の点からも、いい取り組みだと思います。