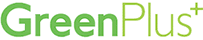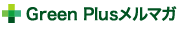醸造蔵から半径50マイル(80キロメートル)で収穫された大豆、小麦を使ったしょうゆの生産に取り組む藤崎町の中村醸造元(中村充滋社長)が、CO2削減に努める食品企業を表彰する「2009年度食品産業CO2削減大賞」で農林水産省総合食料局長賞を受賞しました。
醸造蔵から半径50マイル(80キロメートル)で収穫された大豆、小麦を使ったしょうゆの生産に取り組む藤崎町の中村醸造元(中村充滋社長)が、CO2削減に努める食品企業を表彰する「2009年度食品産業CO2削減大賞」で農林水産省総合食料局長賞を受賞しました。(写真 陸奥新報)
同社は深浦町の黄金崎農場と連携し、食料の輸送距離を表す「フードマイレージ」の低いしょうゆの生産を確立。輸入原料から地元産への切り替えでCO2削減率が98.5%に上ることに加え、同農場との契約栽培で採算性が低い小麦を利益作物にしたことなどが評価されました。
同社が地元産の原料を使用したしょうゆ生産に取り組み始めたのは6年前。中村社長は「江戸時代後期の創業時、先祖は近隣で収穫された原料を使っていたはず。本来あるべき姿に戻したかったし、食の安心と安全、自給率向上、CO2削減につながる」と理由を語ったそうです。
同社の大豆、小麦の使用量はそれぞれ年間120~140トンで、これまではインド産大豆、カナダ産小麦を使用。年内にすべて地元産に切り替える予定で、大豆はつがるにしきた農協管内で生産、収穫されたものを使用するそうです。
新たに小麦の焙煎(ばいせん)装置、大豆の洗浄装置の設置が必要になりますが、中村社長は「小さな投資ではないが、地元でできたものをそこで加工し、付加価値を付けて全国に発信したい。大手企業と明確な差別化が図れるし、少しでも地域の経済発展に貢献したい」としています。
近年、消費者の農産物に対する安全・安心志向の高まりや生産者の販売の多様化の取組が進む中で、消費者と生産者を結び付ける「地産地消」への期待が高まってきています。
フードマイレージを知って、意識して国産の食べ物を選ぶことで、自分が出すCO2を減らすことができます。
同社が地元産の原料を使用したしょうゆ生産に取り組み始めたのは6年前。中村社長は「江戸時代後期の創業時、先祖は近隣で収穫された原料を使っていたはず。本来あるべき姿に戻したかったし、食の安心と安全、自給率向上、CO2削減につながる」と理由を語ったそうです。
同社の大豆、小麦の使用量はそれぞれ年間120~140トンで、これまではインド産大豆、カナダ産小麦を使用。年内にすべて地元産に切り替える予定で、大豆はつがるにしきた農協管内で生産、収穫されたものを使用するそうです。
新たに小麦の焙煎(ばいせん)装置、大豆の洗浄装置の設置が必要になりますが、中村社長は「小さな投資ではないが、地元でできたものをそこで加工し、付加価値を付けて全国に発信したい。大手企業と明確な差別化が図れるし、少しでも地域の経済発展に貢献したい」としています。
近年、消費者の農産物に対する安全・安心志向の高まりや生産者の販売の多様化の取組が進む中で、消費者と生産者を結び付ける「地産地消」への期待が高まってきています。
フードマイレージを知って、意識して国産の食べ物を選ぶことで、自分が出すCO2を減らすことができます。
地産地消が地域の連帯感を強め、地場産業の活性化にもつながりますね。
環境ブログランキングに参加しています。よろしければクリックご協力お願い
します。