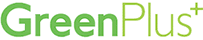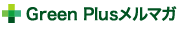下北半島沖一帯の海底下2000~4000メートルには、スポンジ状で気体や液体を吸収しやすい「褐炭」という未成熟な石炭層が広がります。同機構は 06年「ちきゅう」で同半島沖を海底下650メートルまで掘削、CO2をメタンに換える「メタン生成菌」の生息を確かめました。同機構の稲垣史生上席研究員ら は褐炭層にもこの菌がいると予測、厚い粘土層に覆われた褐炭層でメタンへの転換を図る考えです。
課題はメタン生成菌の能力です。地層中では転換に1億年から100億年かかります。研究グループは、褐炭層から溶けだす栄養を効率的に使い、100年以内でメタンに換えるように菌の能力を高める技術を3~5年で完成させることを目指すそうです。
実用化の際には、CO2回収装置のある火力発電所からパイプでCO2を送り込み、生成メタンを採掘して同じ発電所で燃やす方式が考えられます。同機構では東北から北海道沖の褐炭層に、日本の年間排出量の100倍以上にあたる最大2000億トンのCO2が封入可能と推定。将来は巨大天然ガス源になる可能性があります。
CO2を天然ガス化し、持続可能なエネルギーとして海底炭田に封入することに成功すれば、海洋に浮かぶ日本列島にとっては有効な取り組みになると思います。