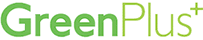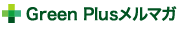先進国の企業や団体が途上国で投資した事業による温室効果ガスの排出削減量を自国分に算定できる同制度で、大学が実施する植林事業を承認したのは初めてだそうです。
今後、国連に正式登録された後に吸収量に見合った排出枠が認定され、民間企業などに売却が可能となるとのこと。

今後、国連に正式登録された後に吸収量に見合った排出枠が認定され、民間企業などに売却が可能となるとのこと。
慶応大は環境分野の国際貢献の一環として、遼寧省瀋陽市で砂漠化や黄砂飛散防止のため、ポプラの植林に取り組んでいます。事業対象は371ヘクタールで、2003年に植林を開始、12年に完了予定。CO2の吸収量見通しは年間平均で1153トンとなるそうです。
事業承認では、植林の継続的な取り組みが中国の環境問題の解決や農村地域の発展に寄与したことが評価されました。
慶応大によると、10年3月ごろの排出枠取得を目指しており、売却収入を中国での環境保全活動に充てることなどを検討しているそうです。
大学として、小規模植林CDM事業としては、世界で初めてのケースとなるこの取り組みが、更なる環境教育の発展・促進を図ってくれるのではと思います。