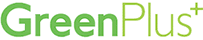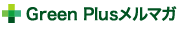なかなか進まない国の議論を横目に、自治体が独自の排出規制に取り組んでいます。今年度から東京都が大規模事業所に義務を課して、排出量取引制度導入したのに続き、埼玉県も来年度から取引制度を始めます。
埼玉県の規制は、対象や削減計画の期間など主な項目で、東京都の制度を緩和したものです。最大の違いは目標を達成できなかった場合でも罰則がないこと。東京都が罰金などがある「義務」と位置づけているのに比べると、制度の甘さが目立ちます。
県外でのCO2削減実績を「排出枠」として、工場では削減目標量の半分まで使うことができる(東京都は三分の一まで)ほか、東京都が認めていない森林吸収量を排出枠に認めるなど、目標の大きな企業でも達成しやすくなっています。制度の対象とする温暖化ガスも「エネルギー起源CO2」に限定。工業プロセスでのCO2排出が半分以上を占めるセメント事業者の負担を大きく軽減しています。
ですが、東京都が罰則付きの厳しい基準を押し切っているのに、埼玉県が何故、概要の発表後も地元の大企業に制度の緩和を迫られているのか。そのわけは、両者の排出量の内訳にありそうです。東京都の排出量の中心はオフィスビルなどの業務部門。都内に本社機能を持つ企業は多いですが、環境面で厳しい規制を打ち出したとしても、首都である東京の拠点をほかに移転しようとする企業は少ないです。一ヵ所あたりの排出量が大きい工場などの産業部門の割合は10%以下。逃げられない相手に対し、薄く広く義務をかけたと言えます。
これに対し、埼玉県の排出量の比率は東京都と、産業部門と業務部門の割合がほぼそっくり入れ替わっています。40%近くがセメント工場などの大口排出者が多い産業部門の排出です。少数の業者に目標が重くのしかかる構図のため、反発も強くなります。
企業の温暖化ガス排出削減の実現は厳しさを増しています。エコな街づくりに向けて、環境負荷の大きな企業に協力を求めることも大きな課題となっています。(日本経済新聞)
環境ブログランキングに参加しています。よろしければクリックご協力お願いします。

県外でのCO2削減実績を「排出枠」として、工場では削減目標量の半分まで使うことができる(東京都は三分の一まで)ほか、東京都が認めていない森林吸収量を排出枠に認めるなど、目標の大きな企業でも達成しやすくなっています。制度の対象とする温暖化ガスも「エネルギー起源CO2」に限定。工業プロセスでのCO2排出が半分以上を占めるセメント事業者の負担を大きく軽減しています。
ですが、東京都が罰則付きの厳しい基準を押し切っているのに、埼玉県が何故、概要の発表後も地元の大企業に制度の緩和を迫られているのか。そのわけは、両者の排出量の内訳にありそうです。東京都の排出量の中心はオフィスビルなどの業務部門。都内に本社機能を持つ企業は多いですが、環境面で厳しい規制を打ち出したとしても、首都である東京の拠点をほかに移転しようとする企業は少ないです。一ヵ所あたりの排出量が大きい工場などの産業部門の割合は10%以下。逃げられない相手に対し、薄く広く義務をかけたと言えます。
これに対し、埼玉県の排出量の比率は東京都と、産業部門と業務部門の割合がほぼそっくり入れ替わっています。40%近くがセメント工場などの大口排出者が多い産業部門の排出です。少数の業者に目標が重くのしかかる構図のため、反発も強くなります。
企業の温暖化ガス排出削減の実現は厳しさを増しています。エコな街づくりに向けて、環境負荷の大きな企業に協力を求めることも大きな課題となっています。(日本経済新聞)
環境ブログランキングに参加しています。よろしければクリックご協力お願いします。