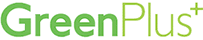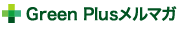カーボンフットプリントとは、商品の原料調達から廃棄までの全行程のCO2排出量を算出して表示する手法のこと。流通業界の呼びかけで、経済産業省が6月に導入に向けたルールの検討を始めた。11月中にも指針が公開される見通しだ。同時に、カーボンフットプリント表示用の統一マークも公表する。
指針は、多岐にわたる商品に共通する原則を定める。下表に示したように、CO2排出量の算定はライフサイクル全体であり、CO2排出の絶対量を商品の本体もしくは包装に表示することなどが書かれている。

とはいえ、指針だけを見ても具体的な算出方法はわからない。詳細なルールは、「商品種別算定基準(PCR)」で定めることになっている。PCRは同一の 商品を提供する企業が集まって決める。カーボンフットプリントは、まず食料品や日用品からスタートし、耐久消費財やサービス分野への展開も視野に入れる。 対象によって算定条件が大きく異なるため、指針には原則だけを記してある。
経産省の検討会に参加した30社の企業は、「エコプロダクツ2008」での試行結果を踏まえて、来年1月にも指針とPCR策定の共通ルールを最終的に固める。その後、国内ルールにのっとった表示品を市場に投入するべく、実 際のPCRの策定を始める。
問題は、PCRを策定する商品の範囲だ。例えば、コンビニで販売しているおにぎりと高級おにぎりを1つのPCRにするか、別のPCRにするかであ る。PCRごとに算定ルールを決めるため、PCRが増えすぎると消費者が表示を比較して商品を買うことができなくなり、カーボンフットプリントの意味が薄 れる。検討会の座長を務めた東京大学の稲葉敦教授は、「PCRが増えすぎないようにコントロールしていく必要がある」と訴える。
来年1月にも始まる国際標準化機構(ISO)での議論をにらんで、欧米各国でも国内ルールの整備が急ピッチで進んでいる。強力なライバルは、表示品の市場投入で先行する英国だが、日本と英国ではPCRの作り方が大きく異なる。
英国ルールは、表示を希望する企業がPCRを作成し、認められればPCRとして成立する。現状では、1社の製品に1つのPCRがある状態だとい う。これでは、せっかくの表示が形骸化しかねない。カーボンフットプリントという新しい表示で、消費者の購買を環境配慮型に変えていくためには、標準化議 論の主導権を日本が取る必要がある。