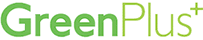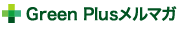環境省の委託を受け、カーボンオフセットに関する情報提供や普及啓発活動を行っているカーボン・オフセットフォーラム(J-COF)によると、新聞報道などで分かっているだけでも、国内におけるカーボンオフセットの取り組みは2008年10月末時点で303件あり、その数は日々、急速に増えている。
きっかけとなったのは、2008年2月に環境省が発表した「我が国におけるカーボン・オフセットのあり方について(指針)」だ。
カーボンオフセットの定義や意義を示すとともに、その手続きや排出量の算定方法、実施に際しての課題などを明らかにした。
同フォーラムのチーフディレクターである竹田雅浩氏は、「以前は環境NGOなど、環境意識の高い人が中心となってカーボンオフセットに取り組んでいました。
最近は一般の事業者がCSR(企業の社会的責任)として、また、他社との差別化を図る手段として取り入れるケースが増えています」と話す。
このように、事業者が主体となってカーボンオフセットを促すのは、日本独特の傾向だ。竹田氏は、「カーボンオフセットが先行している英国では、企業活動によって排出した分を自ら相殺するというパターンが主流」と言う。
きっかけとなったのは、2008年2月に環境省が発表した「我が国におけるカーボン・オフセットのあり方について(指針)」だ。
カーボンオフセットの定義や意義を示すとともに、その手続きや排出量の算定方法、実施に際しての課題などを明らかにした。
同フォーラムのチーフディレクターである竹田雅浩氏は、「以前は環境NGOなど、環境意識の高い人が中心となってカーボンオフセットに取り組んでいました。
最近は一般の事業者がCSR(企業の社会的責任)として、また、他社との差別化を図る手段として取り入れるケースが増えています」と話す。
このように、事業者が主体となってカーボンオフセットを促すのは、日本独特の傾向だ。竹田氏は、「カーボンオフセットが先行している英国では、企業活動によって排出した分を自ら相殺するというパターンが主流」と言う。

この傾向は取り組み内容にも表れている。J-COFでは、商品やサービスを購入する際に、一緒にCO2のクレジットを購入するタイプを「商品使用・サービス利用型」と分類しているが、これが303件中171件と6割近くを占めているのだ。
一方、会議やコンサート、スポーツ大会などの開催に伴って排出されるCO2排出量をオフセットする「会議・イベント開催型」が44件。
英国などに多い、市民や企業がクレジットを購入することで、自らの活動に伴って排出されるCO2排出量をオフセットする「自己活動型」は35件にとどまった。
これら3タイプは、オフセットに用いるクレジットを一般市場を通じて入手できるもので、「市場流通型」とも呼ばれる。
一方、特定の事業主体の間のみで利用される削減・吸収量を用いて実施する「特定者間完結型」も53件あった。
地域の森林保全への出資・寄付行為など、市場を通さずに削減・吸収量を調達するものがこれに当たる。
例えば高知県のある森林組合では、企業から森林整備の協賛金を出してもらい、その整備によって増大する森林吸収量をクレジットとして、知事から協賛企業に無償でCO2吸収証書が発行されるという取り組みを行っている。