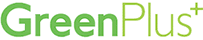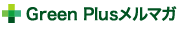京都議定書で日本に課せられた「2008~12年の温室効果ガスの平均年間排出量を1990年比で6%減らす」との目標のうち、3.8%分は森林によるCO2吸収を見込んでいます。
山口県の認証制度はCO2の吸収量、排出削減量、固定量に着目しました。
吸収量は、樹木が育つことでCO2の吸収量がどれだけ増えたかを示します。森林の下刈りや間伐を進めれば、日当たりがよくなって木の成長を促すので、その分数値が上がります。
排出削減量は、木を燃やしてもCO2発生しますが、その木がCO2を吸って成長したことを考えれば差し引きゼロとなることに着目した指標です。ボイラーやストーブに森林バイオマスの燃料を使えば、化石燃料を使った場合に出るCO2量の分が相対的に削減されたとみなします。
固定量は、木材に蓄積したCO2の量。建物に木材を使うと、木材にCO2が長期間閉じ込められることになるため、その分をCO2削減に貢献したとみなします。認証の対象は県産木材を使った場合に限り、利用促進を図るとのこと。
認証を受けたい企業や団体は、県の農林事務所や森林企画課に認証計画書を出します。森林整備を始める際は、森林所有者と協定を結ぶことも必要。県職員が実際に事業の状況を確認し、CO2量を計算した上で、県産の木を使った木製の証明書を発行します。認証されれば、県のホームページに認証者名やCO2量を掲載 し、県が宣伝にも努めるそうです。
山口県森林企画課の担当者は「県という公的機関が認証することで、企業にとっても社会貢献活動のPRに使えるのではないか」と話しているそうです。問い合わせは同課(083・933・3460)へ。(asahi.com)
(山口県/森林企画課/CO2削減認証制度・制度概要)
環境ブログランキングに参加しています。よろしければクリックご協力お願いします。